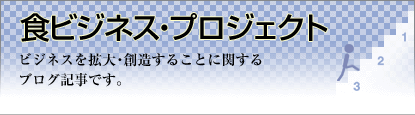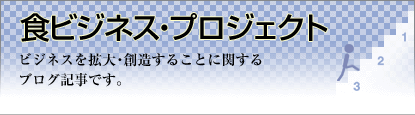ファシリテーター養成講座<基礎編>を 2011年1月に開催いたしました。
これに続く実践編を次のとおり開催いたします。どなたでもご参加いただけます。また、基礎編を受講されていない方でも理解できるよう事例を多く使った内容となっています。
1月に開催しました基礎編で「は観ること・聴くこと・伝えること」について、サイコロジック(心理学+論理)の手法を使ってファシリテーションを学びました。
今回の実践編では、チームや組織の力をいかに最適化し、結果を出させるようにするかをテーマにしています。 各種チームの作り方、チームの中で個人の力をいかに最大限出させるかといった実践プログラムです。
プロジェクトを推進する、サークル活動を推進する、交渉をするなど結果を出せるようにするための実践的なテクニックを中心に勉強します。是非ご参加ください。
*ファシリテーターとは、人と人とのコミュニケーションを円滑にし、相互理解を深めることにより、人と組織をイキイキとさせる技術を持つ人をいいます。
・日時:2011年4月30日(土) 10:00から16:00
・会場:品川区立中小企業センター
東京都品川区西品川1-28-3 電話 03(3787)3041
交通:JR京浜東北線・りんかい線「大井町駅」下車徒歩10分
東急大井町線「下神明駅」下車徒歩2分
・受講料:15,000円(テキスト、昼食代、飲料代込み)