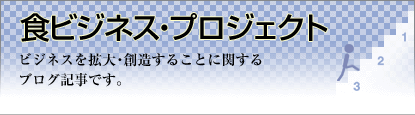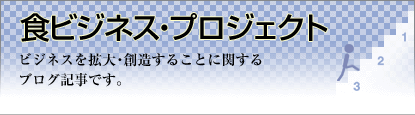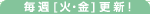
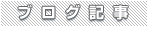
| 彩りのある食や人生(食彩人)についての情報やビジネスのヒントなどを毎週更新します! |
|
|
みなさまからのコメントと
トラックバックについて
個人情報の取り扱いについて
|
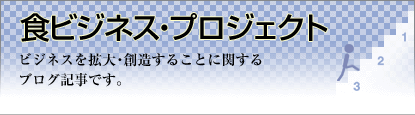
|
|
 |
2007年6月1日 中食シンポジウムを明治大学駿河台キャンパスで開催されました。
2007年6月1日(金) 明治大学駿河台キャンパス紫紺館にて第一回の中食シンポジウムを開催しました。このシンポジウムは、主催:中食ビジネス創造研究会、協力:月刊食品商業で、参加者は、研究会参加企業のほか、食品メーカー、卸、商社、通信、容器包装メーカー、生協、食関連団体、美容、医療そして一般消費者と幅広いものでした。
中食講座と中食セッションの二部構成となっており、中食講座では、明治大学商学部教授小川智由先生に講座をお願いしました。
テーマは、生産の場と消費の場の距離が中食ビジネスのキーポイント
中食ビジネスを創造するためのマーケティング手法についてお話いただきました。(写真)

(中食講座風景)
後半の中食セッションでは、講義いただいた小川智由先生と牟田実(食と生活ラボ代表)と、中食研究は栄養学部や農学部でなくなぜ商学部なのか、最近の学生の食意識調査から見える中食についてセッションを行いました。(写真)

(中食セッション風景)
以下は参加者の皆さんから頂戴しましたご感想の一部です。
●今回キーワードとして出ていた「ブレークスルー」を聞いて、ビジネスの拡大に業界常識や経験が邪魔をするケースもあることを感じました(商社 女性)
●中食はライフスタイルそのものと密接な関係があることをあらためて実感しました(団体 女性)
●中食の定義、明確化などマーケティング理論に裏付けあれたことで自分の中で整理ができました(商社 男性)
●生産の場と消費の場の距離を埋めるというところで、地産地消運動も食品添加物(品質保持剤など)も同じ目的というのがなるほどと感じ有意義でした(メーカー 女性)
●中食のビジネス展開について具体的な例をもう少し聞きたかった(流通 男性)
●ビジネスの観点から中食を分析することは大切であることを実感しました(メーカー 男性)
●もう少し時間をとっていただければよかったと思います(通信 男性)
●時間が少なく、話の深堀までいかずもっと詳しい話が聞きたかった(流通 男性)
●商品やサービスへの価値創造の手法について大いに参考になりました(流通 男性)
この中食シンポジウムおよび中食ビジネス創造研究会に関するお問い合わせは
こちらまで
2007.06.02 10:53:11
| 食ビジネス・プロジェクト
| コメント (0)
| トラックバック (0)
 |
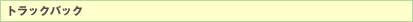
| この記事のトラックバックURL |
http://shoku-labo.com/mt/mt-tb.cgi/821 |
|
|